前にもちょいボヤいた事なんですけどね。
俺は結構な活字中毒を自認していて、年間そこそこの量の本を読んでいます。
最近は再読が多いし、スマホもあるので物理的な紙としての本を買う機会は激減してるんですけどね。
※その割にデジタル本は持っていなかったりとか。欲しい気はあるんですが…ってのはまた別の機会に。
んで、俺が読む主流である文庫本。
その表紙・イラストが、最近かなりの確率で「萌え絵」なんですわ。
言い方を変えれば「漫画絵」「アニメ絵」
記号化され、お約束的な特徴を持った人物像・キャラクター。
あらかじめ言っておくと、俺、漫画もアニメも嫌いじゃないです。いや、好きです。かなり好きです。むしろ趣味の一つといっても(以下略)
でもね、だからといってどこにでも萌え絵を使うべきとは思ってないんですよ。
小説ってのは想像力を喚起させてくれるものです。
映画(動画)→漫画(静止画)→小説と、提供される情報が減る分だけ、読み手の頭の中に想像・イメージが広がります。
これが醍醐味であり、どんなハリウッド的スペクタクル映画も良くできた小説には敵わない。とまことしやかに言われる所以でもあるわけです。
小説には昔から「挿絵」という文化がありますが、これもあくまでも「読み手のイメージを喚起させるもの」であり、どのようにでもとれる抽象的な絵柄が多かったように思います。
そんな良くできた小説の表紙が萌え絵だったら?
頭の中は否応無しに表紙のイメージで固定化されます。
登場人物もその行動にも、漫画・アニメ的なイメージがつきまといます。
繰り返しますが、それが悪いわけじゃありません。
例えばライトノベルと言われるジャンルでは、「キャラクターのイメージ(イラスト)を明確に提示した上で読んでもらう」を前提とすることが多く、これはこれで楽しいものです。
小説家側から「イラストは○○さんで」なんて指定することも多いようですしね。
でも、そうでない小説では。
俺が本屋で、古典的名作ハードSFの表紙が、改訂版で萌え絵になっているのを見て膝から崩れ落ちたのは本当の話です。
これ、もしかすると、漫画が映像化(それも実写で)された時に感じる違和感と同じかもしれません。
※成功か失敗かとは別の話
「どんなキャラなんだが文章じゃわからない!絵で書いてくれ!それも俺の好きな絵柄で!」そんな買い手と「今はこういう絵柄が流行りなんだろ?」な売り手の意見があいまって…というのはうがちすぎでしょうか。
何事にもでもですが「一から全部教えてくれ、でないと判らない、不安だ!」というのは、文化にとって良い方向とは思えないんですよね。
そしてもう一つ「正解は一つ。それ以外はダメ」的な方向性も。
今、映画でシン・ゴジラが話題になっていますが、あれも「あのシーンにはこんな意味がある」「実はこんな裏設定が」なんて情報がばんばん流れていて「だからこう理解するのが正しい」なんて言われてるじゃないですか。
いいじゃないですか、小説も漫画も映画も。
読んだ・見た人がそれで「面白い」と思ったならば。
正解なんて無し。提示された情報の中で自分で読み取った・判断したことが全て。
そして小説に限って言えば、俺は登場人物のイメージは、やっぱり自分で決めて動かしたいんですよねえ。
※ま、安彦良和氏のイラストに惹かれて高千穂遙を読み始めた俺に偉そうなことはいえないわけですが。
(でもまぁ、あれも当時のラノベとも言えるしな)

※撮ったはいいが使い道の無い画像をなんとかしようキャンペーン!
#探せばあるもんだなー
◆↓「バイクカスタム・整備」と「ツーリング」に参加中↓◆
![]()
萌え絵の功罪
 6.バイク以外・趣味・BLOG
6.バイク以外・趣味・BLOG

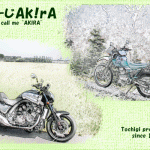
コメント